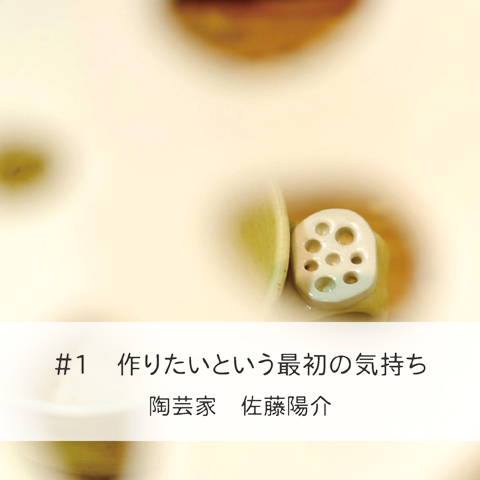商店街と市場の記憶
1995年1月17日阪神・淡路大震災。宝塚市内もとりわけ阪急宝塚沿線の被害は大きく、売布神社駅周辺も、古くからの店が軒を連ねた駅前の阪急ショップセンターや売布市場が全半壊した。「宝塚も結構ひどかったなぁ。御殿山の下の方も結構壊れてたし」と語るのは、宝塚に生まれ育った西迫太志さん。震災当時は小学4年生。通っていた宝塚小学校の築100年超の古校舎は全壊し、卒業までプレハブ校舎で過ごした。同じく全壊した売布市場のそばには昔通っていた幼稚園あったという。「清荒神から友達と2人で1駅電車乗って、売布の駅前から商店街と市場の中を通って通園しててん。確かに古かったなぁ。震災後は、あちこちいつの間にか知らない建物もできながら復興していったって感じかなぁ」。その失われた商店街・市場跡地の復興として持ち上がったのが、防災機能を備えた再開発ビルに映画館をつくるという計画だった。公の復興政策と、忘れ去られたまちの記憶、そして映画館復活を願い地道に活動を続けていた市民の想いが、復興という合言葉の元ひとつに重なったのだ。
50席が背負う、宿命と使命
「さあ、まちに映画館をつくろう」。そこで映画の専門家として宝塚市から依頼を受けたのが、当時映画批評紙・映画新聞の編集発行人であり、開館間もない大阪九条のミニシアター、シネ・ヌーヴォの立ち上げも成功させた景山理さんだった。2年間の準備に関わり、最終的には支配人も引き受けた。できあがった映画館は50席2スクリーン。「日本で一番小さな映画館」を謳う渋谷のUPLINKの40席にプラス10ばかりの客席数には、意外な理由があった。「そもそも国土法の関係で50席以上の映画館は作ることができないという制限があったんです。とはいえ50席でも200席でも、映画を上映するのにかかるお金は同じですから、利益は出ないぞという厳しい宿命を背負っているようなもの。それでも、震災で壊れてしまったこのまちの人間関係づくりという使命があったので、やるしかないと」。制限に負けず、今後長きにわたってまちの中心になる映画館を。専門スタッフを集め、設備面や運営方法についてはとことんこだわり一からつくりあげた。1999年10月29日「宝塚シネ・ピピア」オープン。約30年ぶりに映画館が蘇った。
上映作品はお客さまの「観たい」という声を大切に選び、最新作のアニメから昔の時代劇まで14年間で1500作品以上。高齢者や主婦、家族連れなどで賑わった。作品名をなぞると、お客さまの顔まで浮かぶ。「特に2001年に上映した『千と千尋の神隠し』では、大人のグループまでみんな「千と千尋」ってね。地域の子ども会向けの早朝貸切上映も予約でいっぱいでしたね」と振り返る。景山支配人の人脈もあり、映画とともにシネ・ピピアへ来館した映画監督も数知れず。半世紀を経て、映画と作り手をまちに呼び戻す呼び水にもなっていった。
押し寄せる「デジタル化」の波
しかし、21世紀に入りまちの映画館を取り巻く事情はどんどんと厳しくなった。宝塚も例外ではなく、2001年に近隣の伊丹、続いて箕面、西宮、尼崎と大きなショッピングモールと2000席ほどもあるシネコンが取り囲んだ。一日中遊べる商業スペースを有した大物たちとの戦に敗れ、閉館していった映画館も少なくはない。輪をかけるように映画のシステムも急速に変わった。「映画のデジタル化」と呼ばれる革新により、フィルムを借りて上映するという長年の上映形態は、DCPと呼ばれる専用のデジタル機器を使ったデータ通信方式へと急速に切り替わった。2013年春には大手配給会社の新作フィルム配給はなくなり、 いよいよ新しい機器がないと新作映画をかけることができない。スキームにのれない地方の小さな映画館が閉館に追い込まれる中、シネ・ピピアも導入費用が確保できぬまま春が迫った。 せっかく蘇った映画館が、時代の流れで消えてしまってよいのか?そうして起こったのが、先の署名運動だったのだ。
かき集められた署名
「シネ・ピピア、実は小学生の頃子ども会の企画で行ったことがあるんです」というのは、宝塚で育った大学2年生、乾隼人さん。当時観た映画は『千と千尋の神隠し』。忘れられない思い出もある。「主人公の千尋の両親が豚になってしまうシーンで、隣で観ていた友だちが泣き出してしまって。自分の両親も豚になったらどうしようって。他の友達とその子のお母さんと一緒に、大丈夫だよってなぐさめていた記憶しかないんですけど」。それから11年、小学2年生だった少年も今や大学生。そんな彼の耳に飛び込んできたのが、映画館存続のための機器導入を求める署名運動だった。「当たり前にあるものがなくなる訳がない」と信じたい気持ちと心配な気持ちの間で揺れながらも、学校の友人にも声をかけて署名をかき集めた。「導入決定!と聞いた時は〝ほらな、大丈夫やったやろ?〟って勝手にほっとしていました。誰に言うでもないんですけどね」 。集まった5000人の署名。それは開館からの14年間、いやもっと昔の撮影所時代まで、まちの人の思い出や思い入れ、小さな想いが集まった結果だったに違いない。
映画の都に寄せるもの
晴れて新しい機器の導入が決まった4月の第3日曜日。シネ・ピピアのロビーでは市場がひらかれていた。「シネマルシェ@タカラヅカ」 映画館をもっとひらかれた場所にしたいという想いから、スタッフが陶芸作家やパン職人などまちの若い作り手に声をかけ少しずつ広まったというこの企画。映画を観にきた人や市場を覗きにきた人が行き交うロビーには、在りし日の市場の面影すら重なる。その日は地元のアーティストが集まりロビーでの演奏会で賑わっていた。
マルシェを横目に色とりどりの映画ポスターが並ぶ賑やかなロビーから一歩中へ入ると、スタッフルームがある。壁ひとつ隔てた映画館の舞台裏は、ロビーとは対照的に驚くほど静かだ。おもてのシネ・マルシェでの賑わいを振り返りながら、映画館設立前からのまちと映画館の道のりを一つずつ辿り「映画館にとっては厳しい時代ですけど、人の集まる場所として、もう一度初心に返って自分たちから発信していこうと。何はともあれ、続けていくことに意味がありますから」と語る景山支配人。スタッフルームに積み重なる配給会社との伝票や申請書類たちは、支配人の「続ける」という言葉を体現する地層のようにも見えた。
一方、開館から14年続く「宝塚映画祭」の運営会議には新たに5名のまちの学生が加わり、乾くんの姿もあった。毎年11月、シネ・ピピアの1スクリーンを一週間借りて行われる市民ボランティアによる映画祭。運営スタッフは編集者、カフェオーナー、WEBデザイナー、学生など、職業も世代も様々だ。シネ・ピピアの署名運動も経た今年は「まちの映画館の可能性」をテーマに企画会議が進む。まちの映画館がこれからも続いて欲しい。だからこそ、宝塚映画とシネ・ピピアという2つの軸足は残しつつ、どれだけ離れたことまでできるか?半年後の開催に向けたアイデア出しは続く。 最年少の乾くんも「撮影所があったと言われても、どこか遠い昔の感覚もあるんですけど。まちの歴史と映画館に軸足を残してという考えが気に入っていて、僕は映画館を軸にどこまで色々なことができるかを考えていきたいです」と目を輝かす。まちの歴史としての映画を土台に、ただ映画を観る場所という枠を超え、人が集まり繋がる場所へ。映画館を囲う新しい人の輪が、少しずつ広がりつつある。
時代が変わればまちも変わり、人も入れ替わる。20世紀につくられたあらゆるものが変わりつつある今、まちの生み出したものや記憶を引き継ぐことは簡単なことではない。 かつて「映画の都」と呼ばれた宝塚も、「映画の黄金時代」の終焉とともに映画製作所は姿を消し、その記憶も途切れかけた。しかし、撮影所時代の職人たちが生み出した作品と人々の記憶は、約30年の月日を経て蘇った映画館へと寄せられ、映画のデジタル化という大きな変化を乗り越えるひとつの力にもなった。「続ける」ことが難しい時代。それでもこのまちと小さな映画館が歩んできた道が途切れぬよう、そしてこれからも続くよう、そっと見守りこの記憶を後世につないでいきたい。
Interview,Writing,Photo :藤田理代(michi-siruve)
2013年4月取材
毎月第3日曜日の午後、市場に変わった映画館のロビーに若手作家が店をひろげ、お客さんで賑わう。